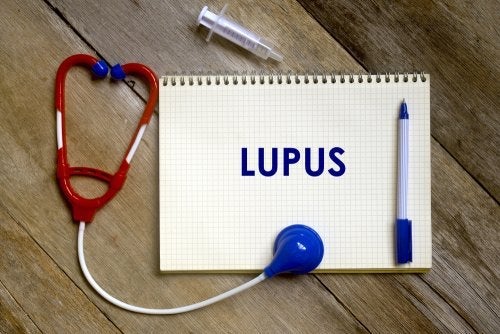過敏性腸症候群を抑える5つのお茶


によってレビューと承認されています。 体育教育学者、栄養士 Elisa Morales Lupayante
消化器官に異常があり、腹痛を起こしやすい状態のままで症状が進むと過敏性腸症候群(IBS)になってしまいます。便秘と下痢の原因にもなります。
最近では、偏った食生活や長時間座り続けなければならないことが増えたため、患者数は増加傾向となっています。
どの年代の人も発症する可能性がある病気ですが、特に10代や20代前半の若い世代に多く見られます。症状は突発的だったり、外部からの刺激によって起こる事もあれば、繰り返し症状が現れる事もあり、腹痛・ガス溜まり・お腹のハリ感など不快な症状であなたを苦しめます。
きちんと対処しないと症状は悪化してしまいますが、嬉しいことに、お茶による自然療法があり、とっても安全なので副作用に悩まされることなく優しくケアする事が出来ます。
さっそくご紹介しましょう。
1.セージティー

セージは収れん作用やイライラを鎮める効果のある植物です。過敏性腸症候群の症状を抑えるには理想的な成分が含まれており、それらが腸の細菌フローラに有効に働きかけ、便秘や腸内の炎症を防止してくれます。
材料
・ティースプーン一杯の乾燥セージ
・カップ一杯の水
作り方
・水を沸騰させ、そこへセージを加え、10~15分ほど浸出させます。
・十分に冷めたら濾して飲みます。
飲み方
朝に一杯、夜に一杯飲む。
2. フェンネルシードティー
フェンネルシードは消化に良いことや、イライラを鎮めてくれることで有名です。過敏性腸症候群の症状も同じように抑えてくれます。また、お腹の膨満感の解消にも効果を発揮してくれます。腸に溜まったガスや毒素を外へ排出してくれる働きがあるおかげです。
材料
・カップ一杯の水
・ティースプーン一杯のフェンネルシード
作り方
水を沸騰させてから冷まし、フェンネルシードを加え15分ほど置いた後、濾して飲みます。
飲み方
毎朝、朝食時に一杯飲み、メインの食事の前にも一杯飲んで下さい。
こちらもお読みください:胃腸に溜まったガスに効果的な5つのお茶
3.アニスティー

アニスティーはイライラを鎮めてリラックスさせてくれるお茶です。
胃のけいれんやおならの発生を抑制してくれます。胃腸の働きを整えてくれるので過敏性腸症候群にも効果的です。
材料
・ティースプーン一杯のアニス
・カップ一杯の水
作り方
水を沸騰させてアニスを加えて10分ほど浸出させた後、濾してから飲みます。
飲み方
メインのお食事の前に飲んで下さい。
4.ミントティー
ミントは消化不良などの症状や結腸異常に最もよく使われる植物の一つです。抗けいれん、鎮静、抗炎症の効果があり、腹部の痛みやハリ感を解消する働きがあります。
材料
・カップ一杯の水
・ティースプーン一杯のミントの葉
作り方
お水を沸騰させてミントの葉を加えます。
蓋をして10~15分ほど浸出した後、濾してから飲みます。
飲み方
朝食時に一杯飲み、一日に2~3杯飲んで下さい。
こちらもどうぞ;きっと気に入る ミントを使った5つの自然療法
5.レモンバームティー

レモンバームティーは消化作用に優れ、腸のガス発生を抑えるのに最適です。抗炎症の効果があり、腹部の痛みの緩和に役立ちます。
材料
・ティーカップ一杯の水
・テーブルスプーン一杯の乾燥したレモンバームの葉
作り方
お水を沸騰させます。沸騰し始めたときにレモンバームを加え、弱火にします。それからさらに2~3分煮出します。3分後火からおろして十分に冷めるまで待ってから飲んで下さい。
飲み方
朝食時に一杯と、お昼過ぎにもう一杯飲んで下さい。
最高の結果を得る為にはヘルシーで健康的な食生活を心がけましょう。脂肪分、糖分、炭水化物の摂取をバランスよくコントロールし、アルコールやカフェインの過剰摂取やタバコは避けましょう。
引用された全ての情報源は、品質、信頼性、時代性、および妥当性を確保するために、私たちのチームによって綿密に審査されました。この記事の参考文献は、学術的または科学的に正確で信頼性があると考えられています。
- El-Salhy, M., & Gundersen, D. (2015). Diet in irritable bowel syndrome. Nutrition Journal. https://doi.org/10.1186/s12937-015-0022-3
このテキストは情報提供のみを目的としており、専門家との相談を代替するものではありません。疑問がある場合は、専門家に相談してください。