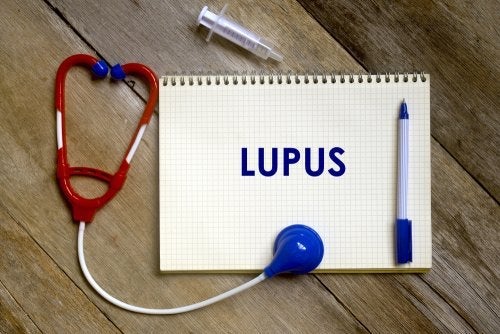唾液分泌過多症の特徴と治療法を学ぼう!

唾液分泌過多症(流涎症)とは、私たちが一般的な言葉で「よだれが出る」と呼んでいるものです。もちろん、この状態は生後15〜36か月の子供の間では正常な症状です。ただし、4歳以降に発生した場合は、異常な状態と見なされます。今回の記事では、唾液分泌過多症の特徴と治療について詳しく見ていきます。
唾液分泌過多症(流涎症)は外見にのみ影響する状態だと考えられることもありますが、実は、深刻な健康状態と関係している可能性があります。深刻な健康状態の中には、例えば、脳性麻痺やパーキンソン病が含まれます。また、妊娠や特定の薬の服用が原因である可能性もあります。
唾液分泌過多症とは何ですか?その原因は何ですか?
唾液分泌過多症は、唾液を口の中に保持して消化管に向けることができないことを特徴とする状態です。唾液の過剰な産生またはその処理において、何らかの異常が発生している状態です。
唾液分泌過多症の中でも、最もよくある原因は神経疾患です。その中には、前述したように、脳性麻痺とパーキンソン病があります。ただし、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、ライリーデイ症候群、または脳梗塞の影響を受けている人にも発生します。
さらに、唾液分泌過多の状態は、抗精神病薬、睡眠薬、または精神安定剤を服用している人にもよく見られます。同様に、妊娠2週目から4週目までの妊娠中に唾液の産生が突然増加するのはよくあることです。

続きを読む:喉が痛いときの対処法
唾液分泌過多症の特徴
唾液を生成する働きがある唾液線には、耳下腺、顎下腺、そして舌下腺の3つがあります。最初の耳下腺は水っぽい唾液を生成し、他の2つは継続的に濃い液体を生成します。これは、窒息を引き起こすことが多い唾液の種類です。
唾液線は、毎日およそ1.5リットルの唾液を生成しますが、その70%は顎下腺と舌下腺で生成されています。唾液分泌過多は、別のより深刻な状態に発展する病気ではありませんが、個人の生活の質に深刻な影響を及ぼします。
唾液分泌過多症の治療を専門とする特定の医師はいないため、唾液分泌過多症の疑いがある場合は、一般診療をまず最初に受診する必要があります。その後、唾液分泌過多症の原因に応じて、専門医を紹介されます。
唾液分泌過多症の分類
原因という観点から、唾液分泌過多症状は2つのタイプに分類することができます。
- 前唾液分泌過多:唾液の過剰産生が神経筋欠損症に起因し、口角や下唇から液体がこぼれる原因になります。
- 後部唾液分泌過多:問題が舌から咽頭への唾液の流れに起因する場合を指します。
トーマス=ストーネルとグリーンバーグの評価尺度によると、唾液分泌過多症を、その重症度または頻度に従って分類することができます。
次のような分類があります。
- 口渇
- 軽度(唇の濡れ)
- 中度(唇とあごが濡れている)
- 重度(服などが濡れる)
- 過度(衣服、手、調理器具が濡れる)
頻度に応じて、次のような測度があります。
- よだれを垂らさない
- 時折よだれを垂らす
- 頻繁に唾液の分泌過多が起こる
- 絶え間なく唾液が分泌される
唾液分泌過多症の影響
唾液分泌過多症多症には、関連する医学的問題が隠れていることがあります。また、顕著な障害を引き起こすだけでなく、神経学的な問題を抱える患者の症状の管理をさらに困難にします。一般的に、この状態は以下のような影響を及ぼします。
たとえば、唇の表皮剥離、筋肉の倦怠感、皮膚炎、味覚の変化、そして発声の困難などが含まれる場合があります。
物理的な観点から見る最大のリスクは、食物を飲み込むのが難しいことが原因で起こる、誤嚥性肺炎です。患者はまた、口腔感染症にかかりやすいです。
同時に、心理社会的影響が非常に深刻なものになる場合があります。よだれは、介護者でも社会的な拒絶を引き起こします。これはまた、日常生活における活動の通常の行動やパフォーマンスを制限します。
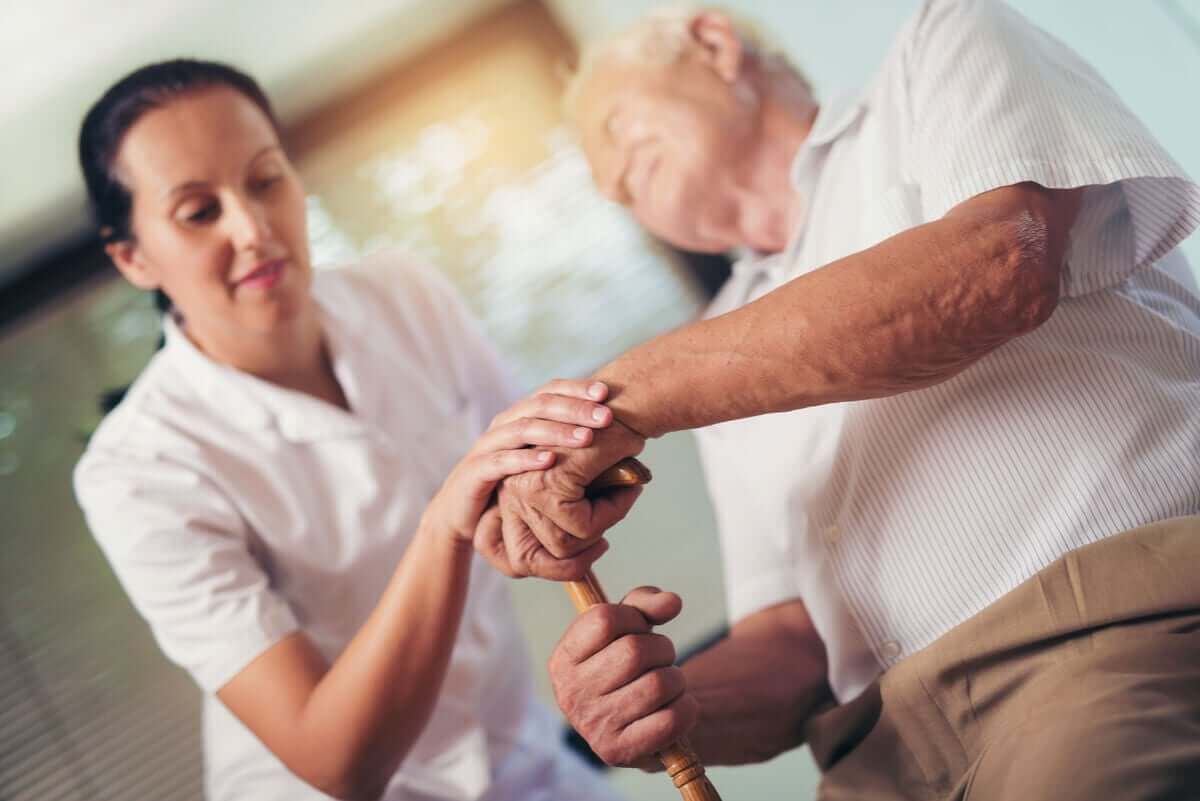
詳細はこちらから:空気嚥下症(呑気症)の症状と特徴とは?
唾液分泌過多症の治療
唾液分泌過多症を治療する3つの方法があります:言語療法、薬理学的治療、そして手術です。言語療法によるアプローチは、病理学的反射を抑制するために一連のエクササイズを行うことが含まれています。具体的には、唇を閉じることと唾液の吸引または嚥下を改善することを目的としています。継続的なトレーニングにより、症状の改善に役立つと考えられています。
薬理学的治療は、唾液の分泌を減らすのに役立つ抗コリン作用薬の服用を含みますが、薬の服用は、言語療法のエクササイズと連動して行われる必要があります。残念ながら、一部の人はこのタイプの薬に不耐性があります。
ボツリヌス毒素A型(TBA)の注射によって唾液分泌過多を治療することも可能です。これは唾液腺に直接適用され、唾液の生成を減らします。副作用がほとんど起こらないのがこの治療の最も良い点です。
最後に、これらの対処方法のいずれも機能しない場合、専門家は外科的介入を行うと決定する場合があります。いずれにせよ、患者ごとに治療方法は異なり、治療の効果を達成するために治療方法を組み合わせることが必要になるでしょう。
引用された全ての情報源は、品質、信頼性、時代性、および妥当性を確保するために、私たちのチームによって綿密に審査されました。この記事の参考文献は、学術的または科学的に正確で信頼性があると考えられています。
- Hernández-Palestina, M. S., Cisneros-Lesser, J. C., Arellano-Saldaña, M. E., & Plascencia-Nieto, S. E. (2016). Resección de glándulas submandibulares para manejo de sialorrea en pacientes pediátricos con parálisis cerebral y poca respuesta a la toxina botulínica tipo A. Estudio piloto. Cirugía y Cirujanos, 84(6), 459-468.
- Silvestre Donat, F. J., Miralles Jordá, L., & Martínez Mihi, V. (2004). Tratamiento de la boca seca: puesta al día. Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal (Ed. impresa), 9(4), 273-279.
- Carod Artal, F. J. (2003). Tratamiento de la sialorrea en enfermedades neurológicas mediante inyecciones transcutáneas de toxina botulínica A en las glándulas parótidas. Neurologia, 18(5), 280-284.
- Rebolledo, Francisco Aguilar. “Tratamiento de sialorrea en enfermedades neurológicas más frecuentes del adulto.” Plasticidad y Restauración Neurológica 5.2 (2006): 123-128.
- Cisneros-Lesser, Juan Carlos, and Mario Sabas Hernández-Palestina. “Tratamiento del paciente con sialorrea. Revisión sistemática.” Investigación en discapacidad 6.1 (2017): 17-24.
- Narbona, J., and C. Concejo. “Salivary incontinence in a child with neurological disease.” Acta Pediatrica Española 65.2 (2007): 56.
- Almirall, Jordi, Mateu Cabré, and Pere Clavé. “Complicaciones de la disfagia orofaríngea: neumonía por aspiración.” Los peldaños para vivir bien con disfagia: 18.
- Pelier, Bárbara Yumila Noa, et al. “Empleo de Kinesiotaping como tratamiento de la sialorrea en pacientes con enfermedad cerebrovascular.” Medimay 26.1 (2019): 88-98.
- Galindo, A. Palau, et al. “Utilidad terapéutica de un efecto secundario para el control de la sialorrea.” Atención Primaria 34.1 (2004): 55.
- Carod Artal, F. J. “Tratamiento de la sialorrea en enfermedades neurológicas mediante inyecciones transcutáneas de toxina botulínica A en las glándulas parótidas.” Neurologia 18.5 (2003): 280-284.
このテキストは情報提供のみを目的としており、専門家との相談を代替するものではありません。疑問がある場合は、専門家に相談してください。